Makoto Kuriya
OFFICIAL WEBSITE
COLUMN
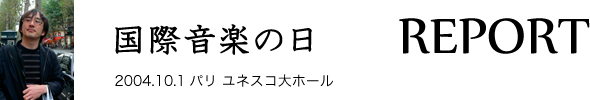
「国際音楽の日」記念音楽祭コンサート・レポート 2004年10月1日、パリのユネスコ本部大ホールで行われた「国際音楽の日」記念音楽祭の写真満載・詳細レポートをお読みください!
赤道を越えて-クリヤ・マコト(2006年10月)

オーストラリアはとても広大な国だ。この広い国で、今回3つの公演を行った。北からブリスベン、シドニー、メルボルン。だけどブリスベンとメルボルンでは飛行機で2時間、本州の端から端までほどの距離がある。メルボルンはいまだにコートがいるような気候なのに、北端のダーウィンという街は常夏のインドネシアと同じ気候だという。こんなにも広大な土地に、たった2000万人の人が暮らしている。
そんなオーストラリアのジャズは、ある意味では閉鎖的、ある意味では極めてアーティスティックだ。総人口が少ないわけだから、音楽産業のマーケットもまた小さい。その中でもジャズという限られたジャンルのマーケットはなお小さい。純粋なアーティスト活動だけで暮らしていけるジャズメンは、ごくわずかしかいない。大抵の人は、別に仕事を持っているという。ある者は音楽院で教え、ある者はレコードのディーラーをし、ある者はラジオのDJをして暮らしている。音楽だけで生活している者でも、普段はロックバンドやポップスバンドのサポートをやって暮らしている。だけどこんな状況の中で、彼らは「ジャズ」という音楽に強いこだわりを持って活動している。そんな彼らが求めるジャズは、それゆえに極めて「狭義」でもあり、また極めて「深い」ものでもあるんだ。
 例えば、メルボルンの街には本格的なジャズ・ライブをやっている店がたった1件しかないという。JAJOも出演した「Bennetts Lane」という店だ。それ以外にもあるにはあるが、「スタンダードをやるピアノバーのような店だ」と地元の人はいう。つまりオーストラリアのアーティストは、BGM的に楽しむスタンダード・ジャズと、アートとして評価する本格的ジャズとをはっきりと分けているのだ。そしてジャズメンが自分の芸術性を追求するステージは、紛れもなく彼らが「本格的ジャズ」と呼ぶものである。何をもって「本格的ジャズ」とするか、その境界線はとても微妙だ。ぼくはこの1年間、その境界線を明確に掴むことができずに悩んだ。これは言葉で説明できるような単純なことではなく、オーストラリアのジャズシーンをかいま見て初めて、漠然と理解できるようなことだった。これを理解して初めて、ぼくは彼らとスムーズに会話できるようになった。
例えば、メルボルンの街には本格的なジャズ・ライブをやっている店がたった1件しかないという。JAJOも出演した「Bennetts Lane」という店だ。それ以外にもあるにはあるが、「スタンダードをやるピアノバーのような店だ」と地元の人はいう。つまりオーストラリアのアーティストは、BGM的に楽しむスタンダード・ジャズと、アートとして評価する本格的ジャズとをはっきりと分けているのだ。そしてジャズメンが自分の芸術性を追求するステージは、紛れもなく彼らが「本格的ジャズ」と呼ぶものである。何をもって「本格的ジャズ」とするか、その境界線はとても微妙だ。ぼくはこの1年間、その境界線を明確に掴むことができずに悩んだ。これは言葉で説明できるような単純なことではなく、オーストラリアのジャズシーンをかいま見て初めて、漠然と理解できるようなことだった。これを理解して初めて、ぼくは彼らとスムーズに会話できるようになった。
そもそも日本では、上記のような区別は極めて曖昧だ。実際「BGM的ジャズと本格的ジャズ」と言葉で言われても、その定義は人によって随分違うだろう。ぼくの印象では、日本のリスナーは音楽の中に「娯楽(エンタテインメント)」の要素と「芸術(アート)」の部分を同時に求めている。ぼくたちは知らずしらずのうちに、「アーティスティックかつエンタテイニング」な音楽を目指しているように思う。いや、もしかしたら一部のリスナーは、純粋に「エンタテインメント」だけを求めているかもしれない。そこへアーティストのエゴゆえに、無理矢理アートを共存させようとしているのかもしれない。だが実際には、一見娯楽的音楽のように見えながら極めて芸術性の高い音楽がいくらでもある。逆にこれみよがしな芸術性を掲げていても、実際には裏付けのない張り子の虎のような音楽もたくさんある。真実は表面的には見えにくいものだ。
 JAJOに参加したアーティストは日本側も豪側も、全員極めて卓越したミュージシャンだった。それだけのテクニシャンが、日本とオーストラリアでは全く違うジャズをプレイしていた。この奇妙さ。今回、両国アーティストの垣根を取り除く一因となったのが、上妻くんの三味線だったような気がしている。ご存知の通り上妻くんはジャズメンではない。だが高い芸術性を持った音楽家であり、同時に日本の伝統をベースにしたアーティストだ。彼の三味線の中に、オーストラリア側アーティストたちは日本人のエスニシティーとオリジナリティーを見いだした。そして三味線の音楽表現を通して、ぼくら日本のジャズメンが潜在的に持っている「日本的な部分」をも、同時に感じ取ってくれたような気がする。
JAJOに参加したアーティストは日本側も豪側も、全員極めて卓越したミュージシャンだった。それだけのテクニシャンが、日本とオーストラリアでは全く違うジャズをプレイしていた。この奇妙さ。今回、両国アーティストの垣根を取り除く一因となったのが、上妻くんの三味線だったような気がしている。ご存知の通り上妻くんはジャズメンではない。だが高い芸術性を持った音楽家であり、同時に日本の伝統をベースにしたアーティストだ。彼の三味線の中に、オーストラリア側アーティストたちは日本人のエスニシティーとオリジナリティーを見いだした。そして三味線の音楽表現を通して、ぼくら日本のジャズメンが潜在的に持っている「日本的な部分」をも、同時に感じ取ってくれたような気がする。
上妻くんがジャズメンでないのと同様に、オーストラリアのジャズを確かに「ジャズ」と言っていいのかどうか戸惑いもある。まず、彼らの音楽はスウィングしない。4ビートもほとんど使わず、変拍子や6拍子系のビートを多用する。コードプログレッションを基本にしたアドリブはやらず(できるんだけどあまりやらない)、フリーインプロを多用する。要するに、これをジャズだと思うから抵抗があるのだろう。もっと大きく「音楽」という枠の中に入れれば何の問題もないんだ。
 オーストラリア・ツアーの初日、ぼくらは初めて長い2セットのステージを踏んだ。1セット目では小編成により、それぞれのアーティストが自分のやりたいことをやるステージが展開した。この約1時間弱のセットを通して、ぼくらは互いの音楽性、芸術性、個性をはっきりと認識することができた。ぼくは今回上妻くんと小編成で「春よこい」をやろうと思ったのだけど、キャメロンはなんと「それなら全員でやろう」と自ら言い出した。誰一人「カバーはダメ」と言う者はなかった。アンサンブルには気持ちが入り、よりタイトになり、インプロヴィゼーションは炸裂した。こうして2セット目を終えたときには、みな喜びでいっぱいだった。キャメロンは「あと2日間で終わりだなんてとても残念だ」と言った。
オーストラリア・ツアーの初日、ぼくらは初めて長い2セットのステージを踏んだ。1セット目では小編成により、それぞれのアーティストが自分のやりたいことをやるステージが展開した。この約1時間弱のセットを通して、ぼくらは互いの音楽性、芸術性、個性をはっきりと認識することができた。ぼくは今回上妻くんと小編成で「春よこい」をやろうと思ったのだけど、キャメロンはなんと「それなら全員でやろう」と自ら言い出した。誰一人「カバーはダメ」と言う者はなかった。アンサンブルには気持ちが入り、よりタイトになり、インプロヴィゼーションは炸裂した。こうして2セット目を終えたときには、みな喜びでいっぱいだった。キャメロンは「あと2日間で終わりだなんてとても残念だ」と言った。
公演は毎日エキサイティングで、ミュージシャンたちはその間ずっと、これからどうやってJAJOを存続させようかという話ばかりしていた。なんてことだろう!6ヶ月前には「オーストラリアのジャズは…」、「日本のジャズは…」とあれこれ分析ばかりしていたメンバーが、今回はそんな屁理屈は一言もこねず、すっかり仲間意識を持っているなんて。3月にJAJOを立ち上げてから半年間、ぼくらは徐々に歩み寄り、衝突し、話し合い、互いを尊重し合いながらここまでJAJOの音楽を作り上げてきた。そして全公演を終了した今、互いに全幅の信頼と、確かなリスペクトを実感することができた。ここに至るまでの困難な「経過」こそが、JAJOプロジェクトの意義なのだと思う。自己主張するにはまず相手を尊重すること、根気強く時間をかけて、決して諦めないこと。JAJOプロジェクトで学んだ多くのことをふまえ、ぼくはこれからもどんどん異文化交流に取り組んでいきたいと思う。世界中の人々と音楽を共有するという夢を、いつの日か実現するために!
JAJOに寄せて-クリヤ・マコト(2006年8月)
先日Rhythmatrixのライブでプレイした「春よこい」が大好評だった。この曲、別にユーミンの曲だから受け狙いでやってるわけじゃない。一番最初にプレイしたのは、タップのカズ(熊谷和徳)のライブだった。その時、ああ、日本のこういう曲ってこんなにもスピリチュアルで、やっぱり日本人の心に染みるものを持ってるんだと思った。その後JAJOのプロジェクトが立ち上がった時、国際交流ユニットだから、何か日本を強く感じさせるペンタトニックな楽曲をやりたいと思った。この時ぼくは、「さくらさくら」じゃなくて「春よこい」だろ、と思った。なぜならこの曲には、日本的要素と洋楽的要素が絶妙にミックスされているからだ。ぼくはこの和と洋の融合こそ、日本人ジャズと欧米ルーツのオーストラリア人ジャズの文化交流企画に最適だと思ったんだ。
 そもそもぼくは、日本に生まれながらジャズが好きでジャズメンになり、ずっとアメリカでアメリカ人とアメリカ音楽をプレイしてきた。鏡の中にのっぺりした東洋人の顔を見なければ、自分が日本人だって事も忘れちゃうような生活だった。ところが、最近ヨーロッパ公演が続き、日本人がアメリカ音楽をやってることの意味、そしてさらにそれを全く関係ない第3国でプレイすることの意味を考えるようになった。東洋人の顔をした男が舞台に出て何かやるというのだから、リスナーとしてはそこに何か「日本的なもの」を期待するのは当然なんだよね。それで、今年のヨーロッパツアーでもぼくは「春よこい」を弾いた。この曲は「洋楽をプレイする現代日本人」であるぼくにとって、しっくりくる題材のようだ。
そもそもぼくは、日本に生まれながらジャズが好きでジャズメンになり、ずっとアメリカでアメリカ人とアメリカ音楽をプレイしてきた。鏡の中にのっぺりした東洋人の顔を見なければ、自分が日本人だって事も忘れちゃうような生活だった。ところが、最近ヨーロッパ公演が続き、日本人がアメリカ音楽をやってることの意味、そしてさらにそれを全く関係ない第3国でプレイすることの意味を考えるようになった。東洋人の顔をした男が舞台に出て何かやるというのだから、リスナーとしてはそこに何か「日本的なもの」を期待するのは当然なんだよね。それで、今年のヨーロッパツアーでもぼくは「春よこい」を弾いた。この曲は「洋楽をプレイする現代日本人」であるぼくにとって、しっくりくる題材のようだ。
ところでJAJOは、3月「しまなみジャズ祭」でデビューした。日豪共に参加アーティストの力量は素晴らしく、初共演はあらかた満足のいくものになった。しかし交流、相互理解という意味では一つの課題が残された。それは文字通り、日豪ジャズのカルチャー・ギャップである。まず、オージー・ジャズはぼくの想像と全然違っていることがわかった。音源はいろいろ聴いていたのだが、実際に共演し、じっくり話してみなければわからないこともあるものだ。最もショックだったのは、オーストラリアのジャズシーンではオリジナルなモノしか評価されないから「カバーは良くない」と言われた事だ。彼らの言わんとする事もわからなくはないが、ジャズとはそもそもハイブリッドな音楽で、様々な素材をオリジナルに解釈しその中に個性を表現してきたものだ。だから「カバーにはオリジナリティーがない」という考えはどうも納得できかった。
 一方、3月のオージー・アーティストたちとの共演を経て、ぼくは「自分のジャズ」を発見することができた。それはきめ細かくドラマを構築し、構築された形の中でいかに自分を自由に解放するか、その中でいかに自分の言いたいことや生き方を表現するかという音楽だった。ぼくはこの時、ごく当たり前だと思ってやってきたそのジャズが実はとても「日本的」、あるいは「東京的」であることに気付いた。これに対してオージー・ジャズはフリー・インプロ中心の音楽で、決め事はごくわずかしかなく、とてもスピリチュアルだった。一言で言ってそれは「オーストラリアそのもの」という印象だった。彼らの音楽の中に、ぼくは漠然とだが、オーストラリアをすっかり見たような気さえした。狭い国土に1億4千万の人間がひしめく日本。他方、自然に打ちのめされそうなくらい広大な国土に、たった2000万人が暮らすオーストラリア。当然両者の感性が同じであるはずがない。どちらが良い、悪いではない。ぼくたちは生き方も、感じ方も、考え方も全てが違うんだ。
一方、3月のオージー・アーティストたちとの共演を経て、ぼくは「自分のジャズ」を発見することができた。それはきめ細かくドラマを構築し、構築された形の中でいかに自分を自由に解放するか、その中でいかに自分の言いたいことや生き方を表現するかという音楽だった。ぼくはこの時、ごく当たり前だと思ってやってきたそのジャズが実はとても「日本的」、あるいは「東京的」であることに気付いた。これに対してオージー・ジャズはフリー・インプロ中心の音楽で、決め事はごくわずかしかなく、とてもスピリチュアルだった。一言で言ってそれは「オーストラリアそのもの」という印象だった。彼らの音楽の中に、ぼくは漠然とだが、オーストラリアをすっかり見たような気さえした。狭い国土に1億4千万の人間がひしめく日本。他方、自然に打ちのめされそうなくらい広大な国土に、たった2000万人が暮らすオーストラリア。当然両者の感性が同じであるはずがない。どちらが良い、悪いではない。ぼくたちは生き方も、感じ方も、考え方も全てが違うんだ。
 おもしろい!!これぞ異文化交流の醍醐味ってもんだ。この共演が無ければ、ぼくは生涯こういう側面から自分の音楽を発見することは無かったかもしれない。オーストラリアがこれほどまでにスピリチュアルな国だということも発見だった。打ち合わせで一度オーストラリアへ行ったが、あの国では時間の流れ方が違う。東京へ戻った途端にせわしなく時間が流れ始める。そんな日常の全てが、音楽にも反映されていく。そしてプレイヤーが違えばもちろんリスナーも違う。音楽はリスナーが育むものだ。リスナーの支持を得ない音楽はやがて消えていく。だからある意味、ぼくの音楽は日本のリスナーが育んだもの、そして彼らの音楽はオーストラリアのリスナーが育んだもの、という側面もあるんだ。実際アメリカ留学していたオージー・ミュージシャンたちは、アメリカでは普通のジャズをやっていたのに、本国へ戻ると次第に変わっていったというから面白い。
おもしろい!!これぞ異文化交流の醍醐味ってもんだ。この共演が無ければ、ぼくは生涯こういう側面から自分の音楽を発見することは無かったかもしれない。オーストラリアがこれほどまでにスピリチュアルな国だということも発見だった。打ち合わせで一度オーストラリアへ行ったが、あの国では時間の流れ方が違う。東京へ戻った途端にせわしなく時間が流れ始める。そんな日常の全てが、音楽にも反映されていく。そしてプレイヤーが違えばもちろんリスナーも違う。音楽はリスナーが育むものだ。リスナーの支持を得ない音楽はやがて消えていく。だからある意味、ぼくの音楽は日本のリスナーが育んだもの、そして彼らの音楽はオーストラリアのリスナーが育んだもの、という側面もあるんだ。実際アメリカ留学していたオージー・ミュージシャンたちは、アメリカでは普通のジャズをやっていたのに、本国へ戻ると次第に変わっていったというから面白い。
確かに、異文化の相互理解は難しい。世界の共通言語だと思っていたジャズですら、こんなにも違っているんだ。だがコラボレーションするからには、それを乗り越えなきゃ意味がない。本当の相互理解が実現したら、世の中の争いだってそれほどひどくはならないはず。だがミュージシャン同士の気持ちも通じないようじゃ話にならない!結局オリジナルとかカバーとか、フォームを論じることに意味はないだろう。重要なのは、ぼくらが提示した題材の中で彼らのオリジナリティーを表現してもらうこと、そして逆に彼らが提示してくれた題材の中でぼくらのオリジナリティーを表現することだ。単に彼らがオーストラリアのジャズを日本に持参し、ぼくらが日本のジャズをオーストラリアへ持参するだけでは、そこに文化交流の軋轢も成果も生まれはしない。さらに踏み込んだコラボレーションを目指すべく、未知のオーストラリアと自分自身を発見させてくれた、彼らとの再会が本当に楽しみだ。
JAJO全公演
 3/18(土): しまなみ音楽祭Jazz Import尾道
3/18(土): しまなみ音楽祭Jazz Import尾道
3/19(日): しまなみ音楽祭Jazz Import今治
3/22(火): Motion Blue YOKOHAMA
9/ 2(土): 東京JAZZ 2006
9/22(金): ブリスベン Power House
9/23(土): シドニー・オペラハウス~Jazz Now Festival
9/24(日): メルボルン Bennetts Lane
9/29(金): 新国立美術館「豪州フェスティバル・レセプション」
JAJO全参加メンバー
 クリヤ・マコト:ピアノ・プロデュース
クリヤ・マコト:ピアノ・プロデュース
キャメロン・ディエル:ギター・プロデュース
寺井尚子: バイオリン・スペシャルゲスト
上妻宏光: 津軽三味線・スペシャルゲスト
フィル・スレーター: トランペット
マット・キーガン: テナーサックス
太田剣: アルトサックス
納浩一: ベース
サイモン・バーカー: ドラムス
大坂昌彦: ドラムス
早川哲也: ベース
ブレット・ハースト: ベース
ジェームズ・グリーニング: トロンボーン・ディジリドゥー



